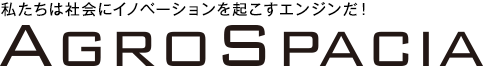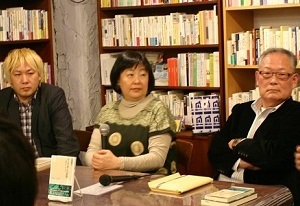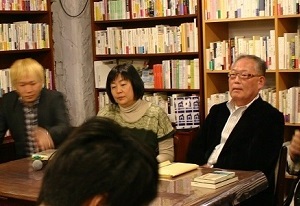第3回 東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ
– 教育大国シンガポールの大学で学んで(インタビュー前編)
シンガポールのリアリティを紹介する木村剛大さんの連載シリーズ。今回はシンガポールに留学中の、エネルギーに溢れる方々にお集り頂いて、座談会形式でお送りします。...read more
第3回 岩渕潤子×村上憲郎×津田大介×玉置泰紀 『ヴァティカンの正体』刊行記念トーク・イベント
質問:一神教と多神教のものの考え方の違いが根本にあると思うのですが、一神教の場合真理というものがあって、考えれば考えるほど真理は到達できる。到達できるからこそ汎用性があって、みんなに伝えることができる。しかし日本では基本は仏教で、しかも、一方では多神教なので、調べれば調べるほどパーソナルなものになって汎用性がない。...read more
第3回 NY:親子でクリエイティブにチャレンジ
伸び伸び楽しむ子供向けのアート体験 ノグチ・ミュージアム
NYのクィーンズ地区、イーストリバーからマンハッタンを望むところにノグチ・ミュージアムがある。誰もが知っている著名な日系アメリカ人美術作家、イサム・ノグチ(1904-1988)により、自身の生涯の代表作を展示するために設計・設立され、1985年に開館した美術館だ。...read more
第2回 岩渕潤子×村上憲郎×津田大介×玉置泰紀 『ヴァティカンの正体』刊行記念トーク・イベント
小さな街ヴァティカンの底知れぬ影響力 この本には学術的な話や文化・芸術の話が密度濃く書かれているが、『ゴッドファーザーIII』についてのところだけ、『実話ナックルズ(ミリオン出版から出ている実話誌)』みたいなダイナミズムがあった…と津田氏は笑いながら話した。...read more
マーク・ニューソン展
– 平和な時代 「アート」としての刀が放つ魅力
2014年3月20日、新橋の東京美術倶楽部で開催された「マーク・ニューソン展」にお邪魔して、本企画のプランニング・ディレクターである永田宙郷氏にお話をうかがいました。...read more
第1回 アイザック・マーケティング株式会社
畠山正己代表取締役に聞く〜データ分析との出会いと変遷
主観的な意見を可視化する“DEMATEL“との出会 第二次オイルショックが起こった1979年、大手広告代理店に入社しました。大学では建築を学んでいたのですが、建設業界に興味が持てず、漠然とかっこよさそうなマーケティングができる...read more
第1回 岩渕潤子×村上憲郎×津田大介×玉置泰紀 『ヴァティカンの正体』刊行記念トーク・イベント
3月1日に『アグロスパシア』で公開した「岩渕潤子×村上憲郎×津田大介×玉置泰紀 『ヴァティカンの正体』刊行記念トークライブ速報」に続いて、その内容を3回にわけて少し詳しく紹介します。...read more
MONO 1st year anniversary party
– 環境に優しい新時代の電動三輪車
東京オリンピックの開催が決定し、ますます環境問題に敏感になる日本。今回は環境に優しい電動バイクのリーディングカンパニー「テラモーターズ」に焦点を当てる。...read more
第5回 中国は世界への扉
上海で元気に働くビジネスウーマン: 伊瀬 幸恵さん
連載第5回目は、グラフィックデザイナー/アートディレクターとして活躍する伊瀬幸恵さんが登場。伊瀬さんは多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業後、同済大学国際文化交流院を修了。7年間日本で広告制作やパッケージ等デザイン業に関わった後、上海に渡り、2008年より上海に在住されています。...read more
ニューヨークの移り変わりを見つめ続けて・・・
創刊25周年を迎えるMetroSource誌創業社長・Rob Davis氏インタビュー
春の訪れをまだ遠くに感じつつも、少しずつ暖かくなりつつある3月中旬のニューヨーク。長期休暇を利用して滞在していた私はMetro Source社を訪れる機会をいただいた。マンハッタン・チェルシー地区にあるオフィスへ訪問し、創業社長Rob Davis氏にインタビューの時間をいただいた。...read more
頭の中はいつもヴェルディ Vol.8
2月5日に青山学院大学において、LGBT (セクシャルマイノリティ) との共生を含む、文化的多様性に関する課題と取り組む「青学BB(Beyond Borders)ラボ」が正式に立ち上がりました。...read more
サンフランシスコのBi-Rite Market
—食を通じたコミュニティづくりという考え方
地元で取れる豊富な魚介類、野菜、果物、ナッツ類、世界的に高い評価を受けているワインなど、新鮮な食材に恵まれたカリフォルニア州のサンフランシスコと周辺のベイ・エリア。もともと風光明媚で、過ごしやすい気候であることから、観光地としても人気が高いが...read more